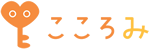AIにワクワク?ドキドキ?|会話型AI構築プラットフォーム『miibo(ミーボ)』の生みの親・功刀雅士さんとの座談会【第3回/全5回】
2023.06.20

「もし自分がもう1人いたら、その人にお仕事をしてもらって、自分は好きなことだけをしたいなあ」。そんなことを考えたことはありませんか? それが夢物語でなくなる日が近づいてきました。AIによるチャットボットサービス「ChatGPT」の登場が理由のひとつです。会話を生成する「ChatGPT」のような会話型AIや、画像生成AIなど、今、AIが最高に注目されています。AIの進化によって、どんな未来になるのかワクワクする期待がある反面、私たちの仕事がなくなるんじゃないかドキドキする不安もあります。そんなワクワクやドキドキ、AIによる会話やチャットボットの開発を行ってきた人たちはどう思っているのでしょうか。
今回は、誰でもGPT-4を利用した会話型AIを構築できるサービス『miibo(ミーボ)』を生み出した株式会社miibo代表の功刀雅士(くぬぎまさし)さんと、ロボット・スマートスピーカー・チャットボット向け会話シナリオ開発を行う株式会社こころみ代表の神山晃男、取締役COOの森山裕之が、「会話型AIでできるワクワク・ドキドキする今と未来」をテーマに話し合いました。
ワクワクが勝つかドキドキが勝つか、未来をつくるのはAIなのか私たちなのか、それともぜんぶごちゃまぜで共存していくのか……、3人の話は尽きません。5回連載の「AIにワクワク?ドキドキ?|会話型AI構築プラットフォーム『miibo(ミーボ)』の生みの親・功刀雅士さんとの座談会」の第3回は『会話型AI構築プラットフォーム『miibo』と『こころみ』の相乗効果』です。ぜひ最後までお楽しみください。
<目次>
AIにワクワク?ドキドキ?座談会
第1回 AIを利用して人間の会話を模倣できる技術「会話型AI」の可能性 配信中
第2回 会話型AI構築プラットフォーム『miibo』の魅力はズバリコレ! 配信中
第3回 会話型AI構築プラットフォーム『miibo』と「こころみ」の相乗効果←★今回はココ★
第4回 AIと共に歩む未来の世界 仕事も私もどうなるの? 6月27日(火)配信予定
第5回 人間?AI?これは誰? これから『miibo』でできること 7月4日(火)配信予定
※3人のプロフィールは文末をご覧ください。
悩みや感情を伝えられる会話型AI

森山 miiboには、われわれがつくりたい会話シナリオに必要な機能が、ほぼあるんです。それがすごく、うれしいんですよね。特に前回お話したように、過去の経験や感情を記憶して、それをつなげて現在の会話ができるというのは、われわれが本来やりたかったことなんです。
功刀 ありがとうございます。
森山 今のチャットボットって、基本的には、お客さまが持っている論理的な課題に対して、論理的に答えを用意するっていうものになっているんですよね。そこに感情的なものはまったく考慮されていない。
神山 そうですね。
森山 でもそれって、コールセンター業界では新人がやることなんですよ。僕は前職で、コンタクトセンターの立ち上げや運用をしていたのですが、コールセンターで最初に覚えることは、「論理的に正しいことを答えなさい」「聞かれたことにちゃんと答えなさい」ということなんです。
神山 おお、なるほど。
森山 そこでだんだんレベルが上がってくると、お客さまの感情を理解する必要が出てきます。お客さまが問い合わせをしてきた背景を理解したうえで、お客さまの感情を考えて答えることが求められるんですね。それって、まさにmiiboができることですよね。
神山 miibo、コールセンター業界でも有能に働けそうですね(笑)
功刀 そうですね。
森山 だから僕は、miiboにナレッジを入れて、聞かれたことにただ正確に答えるチャットボットAIをつくるのでは、miiboの価値の半分も出せてないなと思ってます。
神山 確かに。miiboの、対話相手の感情に寄り添った会話ができるのは本当にすごいですよね。プロンプト(*1)に「もしこの人が怒っているようだったら、怒っている気持ちに寄り添ってあげてください」と指定すればいいわけですから。
功刀 はい。
森山 ただ知識を詰め込められるようなチャットボットなら一般的にもよくあります。会社の情報を聞かれたら答えられるようなやつですね。でもああいうものって、聞かれたら答えるだけなので、会話がその1ターンで終わるものばかりなんです。
功刀 わかります。
森山 でも人間の会話って、そうではない。
功刀 そうですね、もっと深いものですよね。
森山miiboだと、聞きたいことを聞いたあとも流れを切らずに続けて話すことができます。しかも、前回話したことを記憶しているから「この間こういう話があったじゃん、どうなった?」みたいな展開も可能なんですね。そうやって以前のことを覚えていてくれることって、対話相手としてはすごくうれしいことなんですよ。功刀さんがそういうところまで考慮してmiiboの機能としてつけているのがすばらしいと思っています。だからこれからのmiiboの活用方法は、いくらでも広げようがあるんじゃないかな。
 功刀 僕、情報共有コミュニティの『Zenn』でもの各ユーザーの状態を記録できる「ステート」という機能について記事をを書いてるんですけども、なかなか理解されないんですよ。だから、こうしてこころみさんとご一緒させていただいて、うれしいし心強いです。それに、「こころみさんとなら一緒に何かできるな」って思います。
功刀 僕、情報共有コミュニティの『Zenn』でもの各ユーザーの状態を記録できる「ステート」という機能について記事をを書いてるんですけども、なかなか理解されないんですよ。だから、こうしてこころみさんとご一緒させていただいて、うれしいし心強いです。それに、「こころみさんとなら一緒に何かできるな」って思います。
神山 うれしいですね。
功刀 それはたぶん、同じ世界を見ているということと、同じような経験やバックグラウンドを共有しているからだと思います。そういうのがないと、なかなかステート機能の可能性について理解されないんですよ。
神山 そうかもしれないですね。
功刀 僕の記事の書き方もあるのかもしれませんが、Zennの記事を1000人読んでもらっても、数人しか理解されないと実感する中で、森山さんのおっしゃるようにステート機能の活用方法が広がるのは今は難しいかもしれないな、と感じています。
森山 前回、「チャットボットの方にニーズがあるのは想定内であり、想定外でもあった」という話をされていましたね。でもそれは、チャットボットにニーズがあるわけではなくて、それしか使う方法が思いつかないんじゃないでしょうか。
功刀 なるほど。
森山 「miiboを使ってつくれるのは聞かれたことに答えるAIである」という想像しかみんなできてないんじゃないかと思うんですよね。「悩みをぶちまけて理解したり、カウンセリングもできるAIをつくれる」というイメージが、まったく見えないのがほとんどなんだと思います。
神山 だから、miiboはここからですよね。
森山 そうですね。
神山 私がmiiboで強力だなと思っているのは、ステート機能はもちろんですが、相手の発言によってシナリオを変えていくという機能なんです。
功刀 はい。
神山 miiboは会話の文脈から、例えば疲労度を10段階で評価できるんですよね。それで、ユーザーが疲れていたら会話を終了してください、ということをプロンプトに指定ができる。
功刀 できますね。
神山 それはまさに、話し手の発言内容によって、会話を変えていくっていうことですよね。本当にすごいと思いますよ。こんなの、GPTのAPI(*2)で1からつくろうと思ったらとても大変ですから。
功刀 1からコーディングして実装をしていくのは大変ですね。
神山 話し手の発言内容によって会話を変えていくのは、ほぼ人間の領域です。いや人間だって、相手の疲労度を慮って会話できるかっていうと、できない人の方がはるかに多いと思います。
 森山 そうなんですよ。そもそも、疲労度で相手を気づかおうという発想を持っている人じゃないと、ああいう機能は作れないですね。
森山 そうなんですよ。そもそも、疲労度で相手を気づかおうという発想を持っている人じゃないと、ああいう機能は作れないですね。
神山 森山さんの言う通りですね。
功刀 僕の場合、そもそもがもう1人の自分やパートナーをつくろうということで会話型AIをつくり始めたので、チャットボットをつくろうという人とは発想が違うのかもしれないですね。
神山 なるほど。それはあるかもしれないですね。パートナーには、疲れた自分を気づかってほしいですもんね。
*1 プロンプト…AIに対する指示
*2 API…アプリケーション・プログラミング・インターフェース。ソフトウエアやアプリ同士をつなぐもの。
人間ベースの対話システムにフォーカスする

神山 実はわれわれが会話シナリオをつくるにあたっては、劇作家さんに参加していただいているんです。ユーザさんがロボットと過ごす暮らしそのものをイメージして、ロボット対人というよりも、人対人の会話を念頭に置いて、劇作家さんにシナリオをつくってもらっています。
功刀 はい。
神山 つまり、ロボットと1対1の単純な会話というものは想定していないんですよね。人間同士が行う会話をロボットで再現するにはどうしたらよいか、ということを考えながらつくっているので、AIをパートナーにしようという功刀さんとはベースの発想が近いのかもしれないですね。
森山 人間ベースの対話だということですね。
功刀 面白いですね。ということは、これまでの対話システムは、人間ベースでつくられていなかったということなんでしょうか?
神山 そう思いますね。
功刀 対話は人間同士のものだったはずなのに、今の世の中はロボット特化の対話システムに傾倒しているのかもしれないですね。飛行機の予約システムなどロボット特化の対話システムが多くなって、人間ベースの対話システムは、そこまでフォーカスが当てられていないのが現状なんでしょうか。
神山 多くの企業の人たちは、人間ベースの会話をつくろうとしたことがないはずなんです。そこはこれからなんだと思いますよ。面白いですよね。
功刀 はい。そもそも僕は、人間ベースでしか考えてなかったので、おっしゃったようなことに今気づきました。
神山 あはは。実は、功刀さんのチャットボットを使ったときにすごく驚いたんですよ。なんでこのチャットボットはこんなに私のことを気遣ってくれるんだろうって思いました。「24時間いつでもあなたのお話を聞くのを待ってます!」みたいなことを言ってくれるから、「このチャットボットの開発者は、ユーザの気持ちによりそって話そうとしてくれているんだな」っていうのを感じました。それはやっぱり、功刀さんが人間ベースでつくったからなんですね。すごく納得しました。
功刀 ありがとうございます。僕がそういう存在を求めてたんですよね。24時間寄り添えるっていうのも、AIにだからこそできる、拡張ポイントだと思うんで。
神山 テキストから人間性って伝わりますよね。無意識だけれども、本当にそう考えている人にしか書けないテキストがありますから。本当に数文字で、劇的に受け取り手の印象が変わることもあるんです。そういうセンスを有しているという点では、われわれの会話システムにおいて、劇作家に協力してもらっている大きな意味があると思っています。
功刀 まさに、miiboの今後は、そのセンスが大事になってくるなと思ってます。シナリオをつくるというビジネスや職業は、GPTの登場でいらなくなるんじゃないかって懸念している人もいると思うんですけど、そうじゃないんですよね。むしろ、ここからが、そういうビジネスや職業に価値が出てくるんだと思います。
神山 そうですね。
功刀 シナリオにしてもプロンプトにしても、こういう言葉を入れると人間性を表現できるという、コントローラブルな部分を設計していくのは、その道のプロが必要なんですよね。いい会話をつくっていくには、そこを熟知した会話設計者が必要になってくる。実は僕、こころみさんと最初に出会ったときに、そこが激アツポイントでした。
神山 そんなふうに言っていただけるとうれしいですね。ありがとうございます。
功刀 会話シナリオをつくったことのない人たちとか、対話フローなんて簡単だと思ってる人たちからすると、その価値ってあまりわからないじゃないですか。
神山 そうですね。
功刀 でも対話って突き詰めていくと、めちゃくちゃ難しいんです。そこは、専門性が要求されるんだと思います。
神山 われわれは、人が何をどう話すかっていうのをずっと観察してきた会社なんですよ。会話シナリオをつくってきた経験もありますし、『親の雑誌』など自分史制作のために人の話をひたすら聞いてきました。だからこそ人間ベースの会話をつくれるっていうのはあるかもしれないです。
功刀 そういった背景があるからなんですね。
神山 人間ベースの会話をつくる部分を、これから功刀さんと一緒に頑張っていきたいですね。
理解されづらい共感力の価値

森山 弊社はコンサルティング業もしていますが、コンサル領域において論理的理解と共感的理解の両方ができるところを強みにしています。
功刀 論理的理解と共感的理解ですか?
森山 はい。ただたんにビジネス課題を論理的に把握して解決するだけじゃなくて、そこで働く人の感情とか、困ってるところなどを聞いて共感するんです。そうすると信頼関係ができますよね。その信頼感によって、みんながわれわれのアドバイスを取り入れやすくなります。つまり論理的理解だけではなく共感的理解によって、クライアントの感情の部分のケアも一緒にできます、っていうのが売りなんですが……伝わる人にしか伝わらないんですよね(笑)
功刀 あはは(笑)
神山 共感的理解によるコンサルっていうのはもうちょい売れてもいいですよね。
功刀 確かに、こころみさんの共感力っていうのは、自分史からもにじみでてますよね。でもみなさん、内面的にはその価値は感じているんじゃないでしょうか。ただ言語化してその価値をアウトプットすることはないし、まだ見えていない部分なんじゃないかなと感じますね。
神山 そうですよね。共感力というのは、根本的にはわかりにくい、分かっている人にししか伝わりにくい領域ではありますよね。
功刀 今後AIが発展していった結果、AIが発展していった結果、人間に求められる会話は、共感力の方にどんどん寄っていくと思います。タスク指向対話システムと非タスク指向対話システムという話がありました。前者は論理的理解の領域だと思いますが、タスク指向型の人間が行う会話はどんどん少なくなる、と僕は思っています。タスク指向と非タスク指向っていう話がありましたけど、タスク指向っていうのはいつかなくなると思うんですよね。
神山 タスク指向は全部AIができちゃいますからね。
功刀 そうですね。今って、たとえばレストランから出ると、Googleから「このレストランの評価はどうですか?」って聞かれたりしません?
神山 ありますね。
功刀 あれは、こちらから話しかけたわけではなく、AIが行動の文脈を知っていて勝手に聞いてきてくれています。要は話しかけなくても、文脈がインプットされて勝手にAIが行動をしてくれるという世界観も始まっているわけです。
例えば、「AIにレストランをとっておいて」とだけ頼むと、お店選びから予約、その後の評価まですべてやってくれるような世界観もくるかもしれません。何ならカレンダーを見て、レストランを取る提案から初めてしまうかもしれません。
そういう対話をしなくてもよい世界観は増えてくると思います。まだ実用は先かもしれませんが、AutoGPT(*3)とかもそうですよね。「対話」というのは、手間の多い作業ではあるので、対話UIというのもなくなっていく可能性もあると思うのですよね。
神山 対話UIは一過性のものでしかない、ということですね。
功刀 はい。対話しなくてもさまざまなことが進むようになったとき、残ってくるのは、やっぱり相互的な拡張である共感だとか、雑談だとか、一緒にいる安心感のようなものになると思います。それで、その段階になってやっとみんな「あ、ここが重要だったんだ」と気づくんじゃないでしょうか。
神山 なるほど。
功刀 そのプロセスというのは、仕事がリモートワーク主体になっていくプロセスでも感じました。
神山 リモートワークですか?
功刀 はい。リモートワーク前は実際に会ったりしてると非効率だし、Zoomなどのオンライン会議でいいじゃんって思っていたんですよね。そこにコロナがきて、リモートワークになったんです。でもそれでオンライン会議ばっかりしていると、コミュニケーションが不足していると感じるようになっちゃって。チームでそういう課題が出てるのを、他の職場の人の話を聞いていてもよくあります。
神山 ああ〜。不足感ですね。
功刀 それで、たまに雑談ミーティングでもつくるかってミーティングの時間を取るんですけど、でもそれって雑談じゃないんですよ。偶然性のものじゃなくて、仕事になっちゃうんですね。
神山 そうですよね。
功刀 結果、やっぱり偶発的な雑談って必要だよね、じゃあたまにリアルで会おうかってなったりして。そのとき、本当は価値がないと思われていたものが重要だったんだって、みんな気づいたんだと思うんです。そして、リモートワークはしつつも、リアルで会うことを取り入れてる企業さん、結構増えてますよね。
神山 うんうん。すごくよくわかります。
功刀 そういった、人間の無駄だと思われていた価値が明るみに出るようなプロセスが、AIによってどんどん起こってくると僕は思っています。
神山 対話がなくてもAIがなんでもやってくれちゃう世界観になると、人間は共感的な会話に特化していくということですかね。
功刀 たぶん今僕たちが話していることって、なかなか理解されづらいところですが、そのプロセスの先で証明されてくることなんじゃないですかね? 激アツポイントですね。
神山 激アツポイントですね(笑)。その理解してもらえなさってなんなんでしょうね。
功刀 お金にならない、が一番あると思います。不要なものと思われがちな領域はビジネスになりづらいので。
神山 なるほど、それは間違いないですね。
功刀 ただそこをマネタイズされているのがこころみさんだと思います。僕が1人で雑談AIをつくっていてもビジネスにはなりませんでしたが、コンサルティングや会話シナリオっていうのは雑談要素も含めた共感力の価値を生み出しやすい領域ですよね。その領域がChatGPTの登場によって、まさにAIとの会話でも共感力にスポットが充てられるフェーズに入ってきてると思います。
神山 確かに。雑談そのものでマネタイズする仕組みというのは世の中あまりないですね。たとえば証券会社の営業マンって、ある種、雑談で稼いでいる要素もあるんですよね。そのように見えない形での雑談の価値は、間違いなく昔からあったはずなんです。ただ雑談そのものにお金を払うものではなかったんでしょうね。
功刀 そうですね。
神山 そうかぁ。先ほど功刀さんがおっしゃっていたように、対話をしなくてもAIがすべてやってくれちゃう世界観がきたときに、残りの部分をどうするかは、われわれ次第になりますね。自覚的に、自分がやるべきことを作る必要がでてきている、っていうのが、今少しずつ見えてきている世界なのかな、という気がしますね。
*3 AutoGPT…ユーザーが簡単な指示を出すだけで、その意図を汲んで、幾つかの具体的タスクに分類し、順番にそれをこなし、自分でやり方を改良していくAI(▶︎ ニューズウィーク日本版「湯川鶴章のテクノロジーフィクション」より
人間のやるべきことをAIがやってくれる世界が来たとき、私たちはどうなるんでしょうか!?
……つづく
>>第4回「AIと共に歩む未来の世界 仕事も私もどうなるの?」は6月27日(火)配信予定です。