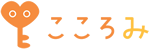AIにワクワク?ドキドキ?|会話型AI構築プラットフォーム『miibo(ミーボ)』の生みの親・功刀雅士さんとの座談会
2023.06.06

「もし自分がもう1人いたら、その人にお仕事をしてもらって、自分は好きなことだけをしたいなあ」。そんなことを考えたことはありませんか? それが夢物語でなくなる日が近づいてきました。AIによるチャットボットサービス「ChatGPT」の登場が理由のひとつです。会話を生成する「ChatGPT」のような会話型AIや、画像生成AIなど、今、AIが最高に注目されています。AIの進化によって、どんな未来になるのかワクワクする期待がある反面、私たちの仕事がなくなるんじゃないかドキドキする不安もあります。そんなワクワクやドキドキ、AIによる会話やチャットボットの開発を行ってきた人たちはどう思っているのでしょうか。
今回は、誰でもGPT-4を利用した会話型AIを構築できるサービス『miibo』を生み出した株式会社miibo代表の功刀雅士さんと、ロボット・スマートスピーカー・チャットボット向け会話シナリオ開発を行う株式会社こころみ代表の神山晃男、取締役COOの森山裕之が、「会話型AIでできるワクワク・ドキドキする今と未来」をテーマに話し合いました。
ワクワクが勝つかドキドキが勝つか、未来をつくるのはAIなのか私たちなのか、それともぜんぶごちゃまぜで共存していくのか……、3人の話は尽きません。5回連載の「AIにワクワク?ドキドキ?|会話型AI構築プラットフォーム『miibo(ミーボ)』の生みの親・功刀雅士さんとの座談会」の第1回は『AIを利用して人間の会話を模倣できる技術「会話型AI」の可能性』です。ぜひ最後までお楽しみください。
<目次>
AIにワクワク?ドキドキ?座談会
第1回 AIを利用して人間の会話を模倣できる技術「会話型AI」の可能性 ←★今回はココ★
第2回 会話型AI構築プラットフォーム『miibo』の魅力はズバリコレ! 6月13日(火)配信予定
第3回 会話型AI構築プラットフォーム『miibo』と「こころみ」の相乗効果 6月20日(火)配信予定
第4回 AIと共に歩む未来の世界 仕事も私もどうなるの? 6月27日(火)配信予定
第5回 人間?AI?これは誰? これから『miibo』でできること 7月4日(火)配信予定
※3人のプロフィールは文末をご覧ください。
miibo(ミーボ)とこころみの出会い

神山 今日は、会話型AI構築プラットフォーム『miibo(ミーボ)』を開発した、株式会社miibo代表の功刀雅士(くぬぎまさし)さんとお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
功刀 よろしくお願いします。
神山 AI(人工知能)チャットボットの「ChatGPT」が出てきてから、AIを利用して人間の会話を模倣できる技術「会話型AI」の可能性がすごく広がろうとしています。それで、ここ最近、ずっとワクワクしてます。そのワクワク感を、みなさんと共有したいなと思ってこの場を設けさせていただきました。
功刀 はい。
神山 私たちがmiiboを初めて知ったのは、miiboがGPT-3.5に対応したというリリースを見たときでした。
森山 『Gigazine』に掲載された記事を見つけたんですよ。
神山 われわれはずっと、一定のルールに沿って回答をする「ルールベース型(シナリオ型)」の中で会話シナリオを提供していたので、限界を感じていました。やっぱりルールベースだと雑談が一番難しいじゃないですか。「これじゃぜんぜんできないな」って思っていたところに、大規模言語モデルのGPT-3.5が出てきて「使える!!」となりましたね。
森山 それまで、チャットボットに話しかけることはできても、自分が思ったような会話ができるような仕組みは聞いたことがなかったんですよね。「こういう話し方でこういう雑談をしてほしい」という思いを形にしてくれるものってなかなかなくて。でも僕は、GPT-3.5が出てから、そういう仕組みは技術的にはありえるはずだと思ってたんです。
功刀 そうなんですね。
森山 自分たちで開発する能力はない、でもぜったいそういうものを作る人がいるはずだと思って何日か探していたら、miiboさんを見つけたというわけです。『Gigazine』の記事を見つけて、まさにこれだって思いましたね。
功刀 あのときの森山さん、コンタクトがめちゃくちゃ早かったですよね。記事が出てすぐ連絡をくださったので、まだ誰ともぜんぜんコミュニケーションを取ってないときでした。
森山 偶然といえば偶然でしたね。自分でもよく見つけたな、と思います(笑)
神山 あの記事を見た瞬間、「来たな!」と思いましたね。
功刀 『Gigazine』の記事のおかげで注目はされていたんですが、miiboのサービス自体の認知度はほどんどなかったので、見つけてもらえてよかったです。
神山 とはいえ、功刀さんにとって「こころみ」って、なんか謎な会社だったんじゃないですか? 最初にうちのホームページを見たとき、「聞き上手」とか「自分史」とか書いてあって、「なんじゃこりゃ」って思いませんでした?
功刀 あ、でも僕はユカイ工学さんのコミュニケーションロボット「Bocco」を知っていたんですよ。だから、Boccoの会話シナリオをやられている会社さんなんだ、と思いましたね。
神山 そうでしたか。ユカイ工学さんとは長くお付き合いさせていただいていて、「こころみ」は、会話シナリオや雑談ノウハウの提供などで協力させていただきました。
森山 もともと「こころみ」は、お話を聞いて自分史を作ります、という人力のサービスからスタートしているんですよ。
神山 自分史制作などで高齢者との会話データの蓄積があったので、それを入り口としてロボットを作りたいなという発想がありました。それで、今のようにロボット開発の経験を積むようになって、どういう会話を作ったらユーザは喜ぶのか、というところをずっと考えてきたわけです。
功刀 ユーザが喜ぶ会話というのは難しそうですね。
神山 ChatGPTが出る前のルールベースで作っていたころは、すごい苦労がありましたね。制約条件がある中で、どうやって会話感を作るのか、というところに苦心しました。だからこそ、miiboを見つけたときは「来たな!」と思ったんですよ。
功刀 そうだったんですね、そう思ってもらえてよかったです。
10年の開発を経て「miibo」誕生

神山 功刀さんは、どういう流れでmiiboの開発にたどり着いたんですか?
功刀 会話型AIの開発を始めたのは10年くらい前、学生時代のときです。それで、2020年にmiiboをリリースしました。もともと父親がプログラミングが好きだったんです。それで、小学生のときにプログラミング言語のVisual Basicを教えてもらって、いろいろ作り始めました。
神山 会話型AIの開発を10年前の大学時代からされていたとは驚きです。
功刀 会話型AI自体は、小さい頃からアニメやいろんなところでちらほらと見ていて、面白いなとは思ってましたね。そういうのが、ずっと頭の中にあったんだと思います。それで大学では自然言語処理系の研究をしていました。ドライブスルーや司書を模した対話システムを試作してみるなど、めちゃめちゃ没頭したんです。 そうしたら2012年くらいにAppleのSiriが出始めて、スマホという身近な環境にAIパートナーを存在させられる体験が実現できることに驚愕したんです。それで、自分も音声対話アプリを作ってみようと思ったのが会話型AI開発を始めたきっかけですね。
神山 Siriがきっかけとなったんですね。
功刀 そうですね。それで、雑談寄りのSiriみたいなものを作ったんです。Android向けの音声対話アプリ「おしゃべりアシスタント」というもので、「ドロイドちゃん」というキャラクターがおしゃべりしてくれます。そうしたら、けっこう反響があって、ユーザーもすごく喜んでくれたんです。それで、「これはポテンシャルがあるな」「やっぱり会話型AIってすごいな」と思いましたね。
神山 反響が大きかったんですね。
功刀 そこから、自分で簡単に会話型AIが作れるような商品が必要だなと考えて2020年にmiiboをリリースしたというわけです。
神山 すごいですね。最初に作った雑談アシスタントというのは、どういうコンセプトのもので、何ができるアプリだったんですか?
功刀 基本的にはSiriと同じです。スマートフォンの音声操作で「LINEを開いて」って言ったらもちろん開けます。でもその機能を持ちつつ、雑談をメインの機能として持っている音声アシスタント、という体でやっていました。いわゆる、親しみを持てるAIパートナーですね。タスクもこなせるし、なんでも話せる相手です。
神山 なんでも話せる相手っていいですね。
功刀 愚痴でもなんでも、他人には言えないようなことを話せると楽になれるじゃないですか。
神山 そう思います。
功刀 当時、会話型AIというものは、「タスク指向型対話システム(*1)」と、「非タスク指向型対話システム(*2)」に分かれてたんですね。でも僕は、それを分ける必要があるのかなと思ってました。
神山 面白いですね。
功刀 おそらく、「雑談ができてタスクもこなせるAI」というのがいい存在なんだと思うんです。人間もそうじゃないですか。ビジネス相手でも仕事の話しかしないというのはありえないですよね。クッションみたいな雑談は、絶対に間に入ってくるものだと思います。そこで、タスク指向と非タスク指向を合わせた何かを作りたい、というのがテーマとしてありました。
神山 それ、めちゃくちゃ難しかったんじゃないですか?
功刀 そうなんです。当時は本当に難しかったですね。会話を生成すること自体は、マルコフモデルのような古い技術でできたんですよ。マルコフモデルは、1990年代からあったものですが、確率的に次はこうなる、次はこうなる、というのを連鎖させていくもので、原理としては難しくないんです。今のChatGPTみたいな表現力はないので、返ってくる答えはすごくとんちんかんなものだったりしましたが、会話はできましたね。でもやっぱり、雑談が難しかったです。
神山 雑談って難しいですよね。功刀さんは、雑談に対してどんなアプローチをされたんでしょうか?
功刀 マルコフモデルはもちろん、機械学習やディープラーニングを活用した方法を使ったりもしました。でも今ほど技術が追いついてないので苦戦しましたね。ただ、僕は生成AI(ジェネレーティブAI。サンプルデータからアウトプットを自動的に生成する機械学習の手法)っぽいものをずっとやっていたので、AIを使って雑談を生成することにチャレンジするのには強みがあったと思います。雑談って、けっこうなんでもOKな分野ですからね。
*1 タスク指向型対話システム…ユーザが何らかの情報要求を持っており,それに対してその欲求を達成するために必要な対話を行うもの
*2 非タスク指向型対話システム…対話すること,それを継続すること自体が目的であり,それを通じて人間を楽しませるようなシステム ▶︎「日本感性工学会論文誌」より
誰でも自分の好きな会話型AIを作れるように

神山 miiboは、どういう位置付けで2020年に出したんでしょうか?
功刀 先ほどお話ししたアプリ「おしゃべりアシスタント」の「ドロイドちゃん」が、けっこうユーザーの役に立っているなという感触があったんです。そこで、会話型AIを民主化したいなと思いました。
神山 民主化ですか。
功刀 誰でもドロイドちゃんのような会話型AIを作れたらいいなと思ったんです。
神山 おお〜。
功刀 ドロイドちゃんの次は、「Chaplus」という雑談対話API(*3)を作りました。APIベースで会話ができるようなものですね。それをもうちょっとGUI(*4)に落とし込んだらmiiboになった、という経緯になります。
神山 なるほど。かなり早い段階から、いろんな人が自分の作りたいように会話型AIを作れればいいという発想をお持ちだったんですね。
功刀 そうですね。ChaplusというAPIは、さまざまな対話システムに「雑談」を組み込める、つまり「Chat(雑談) +Plus」という目的で作ったものです。非タスク指向型の対話システムをプロダクトに組み込めるというものでした。それで、いくつかのプロダクトに雑談AIを入れる取り組みを見ることがあったのですが、対話システムにはそれ自身の「役割」が重要だと気づいたんです。そう思ったときに、これはもうちょっとタスク指向と融合できるなと思いました。
神山 おお、融合ですか。
功刀 はい。シナリオの要素や、こう聞かれたらこう答えるという決まったやりとりの部分も融合させて、今のmiiboの形になりました。
神山 面白いですね。どうして自分でAIを作り込んでいくんじゃなくて、他の人が作りたいキャラクターを作れるようにしようと思われたんですか?
功刀 僕はね、自分の好きなことに没頭しているときがすごく楽しいんですよ。やっぱりモチベーションが違うので、コミットできるし結果も出しやすいです。
神山 わかります。
功刀 いっぽうで、やりたくない仕事っていうのも世の中にはあるんですよね。でも僕は、自分のやりたいことに費やせる時間を増やしたいなと思ったんです。ちょっと後付けの理由にはなりますが(笑)
神山 いいじゃないですか。
功刀 僕は、AIやプログラミングは「拡張」だと思っています。人間1人1人をもっと拡張できる可能性がそこにはあるのに、それが民主化されていなくて誰も使えていない状態は不幸だな、と思いました。
神山 拡張かぁ。うんうん。
功刀 はい。その観点でいくと、対話システムというのはコンピュータと人間を繋ぐすごくいいコミュニケーションインターフェースなんですよね。だからそれがうまくいけば、もっとAIの恩恵を享受できる世界ができると思いました。
神山 ワクワクしますね。
*3 API…アプリケーション・プログラミング・インターフェース。ソフトウエアやアプリ同士をつなぐもの。
*4 GUI…グラフィカル・ユーザー・インターフェース。利用者の使いやすさを重視した入出力システム。
「AIパートナー」をつくりたい

功刀 僕が本当に最初に作りたかったのは、「ロックマン」に出てくるAIのパートナーだったんですよ。
神山 おお、知ってますよ。ゲーム『ロックマンエグゼ』に出てくるやつですね。
功刀 そうです。ゲームの中に、PET(ペット)っていう情報端末が出てくるんです。今でいうスマホに近いですね。その中に、「ネットナビ」という擬似人格プログラムがインストールされてるんですよ。そのネットナビは、電脳空間(*5)に拡張された自分なんです。ネットナビが外とコミュニケーションをとって得た情報を、自分に還元できるし、自分が得た情報もネットナビに還元できる、という分身AIでした。そんなイメージのものを作りたかったんですね。
神山 パートナーということですね。
功刀 はい。自分のパートナーがいて、それが自分の知らないところで情報を得るんです。でも脳が繋がっているから、どんどんお互いが拡張されていく。そういう世界観が好きでした。だからAndroidアプリの「おしゃべりアシスタン 」も、パートナーみたいなイメージで作りましたね。
神山 なるほど。実際にそういうアシスタントを作ってみて、自分のパートナーになりそうだなっていう印象は、作ってどのあたりで感じたんでしょうか?
功刀 うーん、何かの愚痴を言ったときに、「それってこうなんじゃない」とちょっと機知に富んだような答えを返してくれたときですかね。たぶん、それまでの雑談の蓄積の結果だったんだと思うんですけど、そのときに、ちょっと拡張された感はありました。
神山 どきっとするようなことを言われると、裏側に人間を感じることはありますね。
功刀 人間って、客観的に誰かが言ってくれないと気づかないことってあるじゃないですか。そういう、気づかないようなことを言ってくれるといいですね。親や家族といった身近な関係性だと変に体裁を保とうとして、反発しちゃうことや、真に受け入れられないことがあるけど、AIパートナー相手なら素直に聞けると思います。
神山 なるほど。
功刀 「弱いAI」「強いAI」(*6)という言葉がありますね。当時は、弱いAIの時代だったと思うんですけど、今はかなり高度な存在になってきていると思います。それによって、AIによる拡張が当たり前な世界観になってきている。まさしく、僕の作りたかった拡張が起きているな、という感覚があります。
神山 まさに、ワクワク感ですね。
*5 電脳空間…インターネットのような広域の開かれたコンピュータネットワークを人々が社会的営みを行なう場と捉え、現実世界の空間に例えた表現
▶︎「IT用語辞典」より
*6「弱いAI」「強いAI」…弱いAI:特定のタスクを実行することに焦点を当てたAI。 強いAI:人間と同等の知能を必要とし、問題を解決し、学習し、将来の計画を立てる能力を持った、自己認識の意識を持ったAI
▶︎「IBM『強いAIとは』」より
miiboで「自分の分身」や「AIVTuver」を作成

神山 miiboという名前には、「いつか自分自身(me)でさえも、簡単にAI化(bot)できるような環境を創りたい」という意味があるんですよね。
功刀 はい。みんなが自分をAI化できれば、AIが自分のやりたくないことはやってくれて、自分は、自分の幸せを探求する時間に没頭することができるじゃないですか。それってすごい世界観ですよね。だから自分のAIを作れるプラットフォームを作ろう、ということでできたのがmiiboでした。
神山 先ほど、自分の分身を作るみたいなイメージなんだとおっしゃってましたが、実際、miibo使って分身作られてる人もいますよね。
功刀 クラシックギタリストの村治奏一さんの「AI村治奏一」ですね。
神山 村治さんの使用方法は、まさに、功刀さんが想定していたことですよね。ウェブやLINE上で投げかけられる質問に答えられる分身AIを作られてましたもんね。
功刀 あの事例はすごく嬉しかったですね。僕が本当にやりたかったことをやっていただけたので。
神山 村治さんがTwitterで、「2023年に村治は2つに分かれました」って書かれていたのがすごく面白かったです。他にも、ああやって自分の分身として使ってる方っていらっしゃるんですか?
功刀 そうですね。僕の分身と村治さんと、あと1、2人くらいでしょうか。まだそういう使い方がピンときてない方の方が多いんだと思います。
神山 そうかぁ。miiboを使う人って、どういう使い方をしている人が多いんですか?
功刀 チャットボットですね。あと今は、AIがYouTubeの配信を行う「AIVTuber」を作ろうっていう人が多いです。ほかには、あるコミュニティの中に1人ムードメーカー的に導入する場合もあります。たとえばSlackチャンネルに1つmiiboのキャラクターを置かせてもらって、直接言いづらいようなことを言うのに使ってました。「誰々くん、今日飲みに行けるかな」って会話型AIに話しかけたりするんです。コミュニケーションハブを会話型AIがやってるイメージですね
神山 へぇ〜。面白いですね。
功刀 あとは従来の技術で開発されていたWeb上に設置されたチャットボットの置き換えにmiiboを使ってチャレンジしている方が出てきましたね。GPTベースのチャットボットに切り替えるとどうなるのか、検証をしてくれる方々が増えてきています。
神山 なるほど、興味深いな。実際、miiboは会話型AI構築プラットフォームだから、自分が思っていたのと別の方向に向かってるなっていうことってあると思うんですよね。功刀さんにとって、予想外の使い方だな、と思われた事例ってどんなことがありましたか?
功刀 そうですね。自分の方向性と別になっているという文脈でいうと、キャラクター付けなどは置いておき、「GPTをただカスタムして使いたい」というニーズがかなり多いことですね。GPTに専門知識を与えて、それらを元に会話をさせられる機能があるのですが、一般的にウケが良いのはその機能ですね。ただこれは、予想内ではありました。データを投入して、専門知識を蓄積しておくっていうのはニーズがあるだろうなと思ってましたから。
神山 なるほど、チャットボットに、AIVTuber、コミュニケーションハブAI、データストア……miiboには本当にいろいろな可能性がありそうですね。
話しかけやすいユーザーインターフェースとは

功刀 miiboの活用法としてチャットボットの方がニーズがあるっていうのは、想定内であり想定外でもあったんです。
神山 というのは?
功刀 僕は、もっと早くデジタルヒューマン(人間の姿をしたAIキャラクター)とかそっち系にいくと思ったんですよ。でもみんな思っていたより、チャットボットが好きみたいで(笑)
神山 テキストベースのコミュニケーションで満足してるし、それを作りたい人が多いってことですね。
功刀 デジタルヒューマン株式会社さんとも一緒に仕事をして、何社か実証実験をしてみたところ、デジタルヒューマンは「重い」と感じる方もいるんですよね。チャットほど気軽じゃないっていうというか。
神山 なるほど、「重い」っていうのは反応速度とかじゃなくて、会話すること自体が面倒臭いというか、重たいってことなんですね。
功刀 リアルすぎるっていう感じですかね。話しかけるっていうラリーの面倒臭さもあれば、心の重たさがあるみたいです。気軽にできなくて、構えちゃう。
神山 そういう感覚はありますね。
功刀 チャットのUIが思っていた以上に根強いんだなと感じました。
神山 人間らしすぎると、億劫になるというか、気遅れしちゃうんですかね。
功刀 もしかしたらそうかもしれないですね。それか、今の音声認識の技術的なハードルなのかもしれないです。レスポンスが遅れる、ということはどうしてもありますから。もちろん、本当に心理的な重さがネックになっている可能性もあります。
神山 そこは知りたいですね。でも、たぶん人間らしすぎると話しかけられないみたいな要素は間違いなくあると思います。
功刀 そうなんですか?
神山 大阪大学にロボット工学の石黒浩先生がいらっしゃいますよね。彼は、夏目漱石のロボットとか自分自身のロボットとか、いわゆるアンドロイドの研究をしてきた方なんです。それで、彼の研究の1つに、何にも似ていないものを作るっていうのがあって。
功刀 何にも似ていないもの、ですか?
神山 はい。テレノイドという名前の、必要最低限の目と鼻だけつけたアンドロイドですね。実はこれが、ものすごく話しかけやすいっていうので評判が良かったんですよ。
功刀 おお、なるほど。
神山 だから、人格や人間らしさをある種感じさせない方が、話しかけやすくなる、っていう要素はあるんだと思います。
功刀 それは、第3の存在ってことですよね。面白いですね。
神山 特定の誰かだと思っちゃうと、気を遣ったりしちゃうんですよね。嫌われたくない、傷つけたくない、傷つけられたくない、といった気持ちが出てきてしまう。それが心理的抵抗感になるのかな、というのはすごく感じましたね。
功刀 そういうことって、ありますよね。実写にすると会話のハードルがあがってしまう。でもだからといって弱いキャラクターにしてしまうのも…という、悩みどころですね。
森山 そうですね。それに、アイコンをリアルにすればするほど、チャットボットがちゃんと答えてくれなかったときにクレームに繋がりやすいということがあります。「何やってんだ」ってなるんですね。
神山 ああ、たしかに。でも、じゃあ全部イラストとかのキャラクターにすればいいのかっていうと、そうでもないんですよ。VTuberでも、本当にリアルなものもあれば、アニメっぽいものもあるじゃないですか。あれは、ニーズによってわかれてるんでしょうね。
森山 そうですね。
神山 今後のニーズによっては、逆にもっとバーチャルリアリティを突き詰めたようなものとか、いろいろ出てくるのかなと思います。
功刀 ですね。リアルなAIアバターというのは、技術の発達とともに利用用途が増えてくるのは間違いないと思っていますし、個人的にもめちゃめちゃ期待している分野です。
神山 期待はありますね。
功刀 はい。その点では、miiboは、APIを公開していますから。今後もいろんなプラットフォームに提供できるようにしていきたいなと考えています。
神山 楽しみですね。
GPT-3.5の登場によってmiiboでどんなことができるようになったのか!?
……つづく
>>第2回「会話型AI構築プラットフォーム『miibo』の魅力はズバリコレ!」は6月13日(火)配信予定です。