ロボットと一緒につくる今よりちょっとご機嫌な日々| ユカイ工学代表・青木俊介さんとの対談(第3回/全4回)
2022.09.12

「コミュニケーションロボットって何? どんなことに役立つの?」そんな疑問に迫るべく、ロボティクス・ベンチャーのユカイ工学株式会社代表の青木俊介さんと、ロボット・スマートスピーカー・チャットボット向け会話シナリオ開発を行う株式会社こころみ代表の神山晃男の対談を2022年7月に開催しました。
役立つロボットや、ロボットとのコミュニケーション、どんなロボットがあったら将来みんながご機嫌に過ごせるのか……2人の話はつきません。4回に分けてお届けする「ロボットと一緒につくる今よりちょっとご機嫌な日々」。今回はその3回目「モチベーションを上げるロボットと会話シナリオ」です。難しいプログラミング用語も数式も出てこない、ロボットのカクカクしたイメージをまるーくお伝えします。
<目次>
ロボットと一緒につくる今よりちょっとご機嫌な日々
第1回 幸せ感のあるロボット(配信中)
第2回 人とロボットのコミュニケーション(配信中)
第3回 モチベーションを上げるロボットと会話シナリオ 9月12日(月)←★今回はココ★
第4回 ロボットと共にあるちょっとハッピーな暮らし 9月20日(火)配信予定
※2人のプロフィールは文末をご覧ください。
モチベーションを上げるコミュニケーション

青木 モチベーションを上げるようなコミュニケーションもけっこうあるんですか?
神山 もちろんです。やれば褒めてもらえる、というのがそれですね。基本的には、褒められた方が多くの人にとってはいいんだろうなと思います。
青木 そうですね。
神山 もしロボットに怒られたら、嫌になって使わなくなったりするじゃないですか。人間だと強制的に連絡とって、やりなさいって言えますけどね。それは、ロボットの開発上の難しさですね。いかに愛着を持ってもらって、毎日使ってもらえるか。そこに気を配ってセリフを作るのが大事だと思います。
青木 僕ですね、最近、ランニングするようになったんですよ。今までずっと続かなかったんですけど、「NIKE Run Club」っていうランニング中併走してくれるアプリを見つけてからは続けられてます。「まずはリラックスしましょう」っていうところから始まって、「あなたは走り続けています。素晴らしいです」って声をかけてくれるんです。
神山 やっぱり褒められるんですね。
青木 そうです、「ここまで続けられるなんて、こんなに貴重なことはありません」みたいな(笑)
神山 それって、歩いたら怒られたりはするんですか?
青木 いや、怒られたりはしないですね。そこまで認識できるように作られていないだけかもしれないですけど。それで、こういうコンテンツはニーズがあるな、と思ったんです。
神山 本当にそうですね。
ちょっと大袈裟な言い方をすると、人間は理性的であって、やるべきことはちゃんと努力してできるっていう前提が少し前までの常識だったと思うんです。だから目の前にある課題も頑張って解決しようね、という雰囲気があった。でも本当は、頑張らずにできる仕組みや環境がないとできないんですよね。
青木 頑張って解決しないといけないのはよくない状態ですよね。
神山 そうですね。楽しめる状況や心地よい環境を作ることで、結果的に頑張っているのと同じ成果が得られるというのが望ましいですね。
青木 努力を自然に続けられるような仕組みを作ったりね。
神山 情報によって感情を心地よくして、感情を心地よくした結果行動がついてくるような仕組みですね。そういうのがあればすごく効果的だし、これからの世の中で意味があるものとして残っていく気がします。
青木 そうですね。そのためのコミュニケーションというか、声のかけ方ってめっちゃ重要ですよね。
神山 たしかに。言い方とか、そのへんはすごく大事になってくるな。
青木 それはこころみさんに、すごく可能性があるんじゃないですか?
神山 ありがとうございます。その部分は特に、うちのような生身の人間が生身の人間の話を聞くことを重視している会社だからこそできる会話内容だと思っているので、人間にとって何が嬉しいのか?ということを常に考えながら作成しています。
AIにできること、AIにできないこと
 神山 ところで、ロボットのプロジェクトだと、AIというキーワードが必ず出てきますよね。うちは人力でシナリオを作ってますけど、「AIでできるんじゃないですか」って外から見てる人は言ってくる。
神山 ところで、ロボットのプロジェクトだと、AIというキーワードが必ず出てきますよね。うちは人力でシナリオを作ってますけど、「AIでできるんじゃないですか」って外から見てる人は言ってくる。
ユカイ工学さんでは、AIという分野で何か考えていることってありますか?
青木 たとえば雑談ができるようなAIと言われても、雑談はそもそも、技術的にすごく難しいじゃないですか。人間でも難しいくらいですから。
神山 そうですね。そもそも雑談をできる人って少ないですよね。
 青木 飲み屋で隣の人と雑談しろって言われてもすごく難しいし、だいたい盛り上がらない。緊張しますしね。だから、誰とでも雑談できるってすごい能力なんですよね。そこをいきなりロボットがやるのは難しいし、アプローチとしてはよくないな、とは思いますね。
青木 飲み屋で隣の人と雑談しろって言われてもすごく難しいし、だいたい盛り上がらない。緊張しますしね。だから、誰とでも雑談できるってすごい能力なんですよね。そこをいきなりロボットがやるのは難しいし、アプローチとしてはよくないな、とは思いますね。
神山 うんうん。
青木 AIの活用法として、人の気持ちや状態を物理的なセンサーで測る、というのはあるとは思います。
神山 それはありますね。情報収集としてのAI活用。
青木 人をよい状態に持っていったり、環境をお膳立てしたりというのは、AIにもうまくできるんじゃないかな。声かけも、そういう環境のお膳立ての一つだと思うんですけど。
神山 いまご一緒してるプロジェクトもまさに、IoTを使っていかに情報を取るかが重要なので、青木さんがおっしゃっていることに近いと思います。その上で、アウトプットは人間が作った会話シナリオなどのコンテンツを提供して、フィードバックを回して、っていう感じですね。
青木 そうした情報収集から会話シナリオの仕組みがうまく回るコミュニケーションロボットは、ユーザのモチベーションを上げるポテンシャルもありますね。
神山 たしかにユーザの年齢に関係なく、そういう効果は大きいと思います。
青木 人って、どうでもいいことですぐ死にたくなったりするじゃないですか。連休の前に飲みすぎて起きたら昼過ぎで、やる気なくなって掃除とかもしたくなくなって寝ちゃって。すぐそういうループにすぐ陥ってしまいがちですけど、そういうのをコミュニケーションロボットがなんとかできるんじゃないかな。
神山 僕も、BOCCO emoの仕事をやっていて、これは別に全世代に効果があるよなって思ったりもします。普通に毎朝おはようって言われるだけで嬉しかったりとか、おかえりって言われただけで嬉しいとか。
モチベーションを上げるロボット会話シナリオと、情報収集としてのAIの活用法が組み合わされば、新しいプロダクトができると確信しているんです。
青木 うんうん。
ロボットと人との信頼関係

神山 モチベーションをあげたりしてくれるAIやロボットを信頼するきっかけって、なんですかね? 愛着を持てるきっかけというか。
青木 こいつの言うことを聞こうっていうきっかけですね。
神山 そうですそうです。
青木 NIKEのアプリのときは、併走して喋ってくれるのが、プロのランナーだったんですよ。自分も競技をやってました、みたいな自己紹介が始めにあって、コンテンツにプロフィールも載ってました。
神山 それは、本当の人間が後ろにいてユーザに協力している、というコンテンツなんですね。
青木 そうですね。だから、話を聞こうって気になりましたね。
神山 なるほど。そうじゃなかったら、「お前は何者なんだ」となりますもんね。
青木 「お前は何者なんだ」っていうのはけっこう重要ですね。
神山 重要ですね。それこそ、うちで会話シナリオを作るときも、事前にバックグラウンドストーリーをきちんと作るんですよ。「『こいつは何者で、どこからきて、なぜユーザの世話をしたいと思っているのか』という動機付けを説得力のある形で作らせてください」とクライアントの方にもお話しています。
青木 こころみさんは初めの頃、高齢者の人に実際に会いに行ってましたよね。会話シナリオではなくて、見守り電話のサービスの「つながりプラス」の方で。
神山 ああ、そうですね。信頼関係を作るために会いに行ってました。あれは大変でしたよ(笑)
青木 やっぱり会いに行くと、「信頼」という点で全然違いますか?
神山 違いますね。一度生身で会った人に対する信頼感というのは、そうでない人に対する信頼感と全然違います。
青木 そうなんですね。
神山 たとえば1回会ってから見守り電話をする人の信頼感レベルに行くまでは、会わずに始めて3カ月くらいかかる感じです。肌感覚ですけどね。
逆に言うと、時間をかければ会ったことがなくても心は開いてもらえる、というのが見えたので、最終的には会わなくてもいいかなってことにはなりましたね。
青木 うん、うん。
神山 そういう、人対人のサービスのときも、バックグラウンドストーリーを大事にしようと思ってるんです。なんでこの人が電話してくるのかっていうのを、見せるんですね。もちろん、見守りサービスであるという前提はあるんですけど、単純に聞き手があなたのことにすごく興味がありますっていう姿勢を示す。それは、かなり気をつけてやってはいますね。仕事だから聞いてますだけだと、話し手は面白くなくなっちゃうんですよね。だから単純に、その話が面白いから聞かせてください、というスタンスをちゃんと出しながら聞く。これはテクニックですね。自分が興味があるんです、ということを示しながら聞くのは、すごく大事だなと思いますね。
青木 なるほど。例えば自分史サービス『親の雑誌』では、歴史としての昔の話に興味がある、という聞き方はするんですか?
神山 それはね、やらないんですよ。
青木 それはあまり刺さらない?
 神山 刺さらないというか、それは、「あなた」に興味があるんじゃなくて、「あなたの話」に興味があるということなんですね。話よりあなたそのものに興味があるっていう方が大事なんです。だからたとえば、「東京大空襲がありました。何万人も死にました」という話に対して、「どれくらいの方が亡くなったんですか?」に興味を強く持たない。もちろんそこも大事なんですけれども、「そのときあなたはどんな気持ちだったんですか?」っていうことを聞いた方が、人は話したくなるんですね。人はやっぱり、自分の気持ちを相手に伝えたいので。
神山 刺さらないというか、それは、「あなた」に興味があるんじゃなくて、「あなたの話」に興味があるということなんですね。話よりあなたそのものに興味があるっていう方が大事なんです。だからたとえば、「東京大空襲がありました。何万人も死にました」という話に対して、「どれくらいの方が亡くなったんですか?」に興味を強く持たない。もちろんそこも大事なんですけれども、「そのときあなたはどんな気持ちだったんですか?」っていうことを聞いた方が、人は話したくなるんですね。人はやっぱり、自分の気持ちを相手に伝えたいので。
青木 うん、うん。どれだけ大変だったのかとかね。
神山 はい。そのときの心細い気持ちや、空が真っ赤でもうダメだと思った、という「あなたの感じたこと」に興味があるんです、という聞き方の方が望ましいんですね。
青木 そうなんですね。じゃあどっちの方向から飛行機が入ってきた、とかはあまり重要じゃないんですね。
神山 実はそこは難しいところで。ディテールを聞かないと、イメージが共有できないので、そういうことは聞くんですよ。「その飛行機はどっちから来たんですか?」と聞きながら話を盛り上げていくんですけど、それを聞く理由というのは、面白い記事を作るためじゃないんですね。あなたがそのときどんな気持ちでいたか知るために当時の状況が知りたいんですと、そんな感じでやってるんです。
青木 なるほど。
そういえば、ちょうど僕の友人が自分史作成サービス『親の雑誌』を作成してとてもよかったってFacebookで言ってましたよ。あの投稿見ました?
神山 はい、教えてもらいました。とても反響あって、突然申し込みがぽんぽんときて、何かなと思ったらその投稿があったっていう。すごい効果がありました。ありがたいです。
どこまでできるかわからないですけど、僕はBOCCO emoでも、「あなたに興味があるんです」っていうのを表現したいんです。会話でだけじゃなくて、UX全体で、ユーザへの興味を伝えるということを目指したいですね。
役に立つことをやろう、とプログラミング的思考だけしていると、そこにはいかないじゃないですか。さぁ、健康の指標を測定しましょう、っていうだけだと、ユーザへの興味は伝わらないですからね。
青木 うんうん。
神山 朝起きて寝るまでの、どのタイミングで話しかけて何をやると、「あなたに興味がある」あるいは「あなたの気持ちに興味がある」っていうのを伝えられるかって、そこを追求したいなと思っているんですよね。
青木 いいですね。

……つづく
>>第4回(最終回)「ロボットと共にあるちょっとハッピーな暮らし」は、9月20日(火)配信予定です。
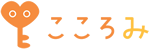

 ■神山 晃男●かみやま あきお
■神山 晃男●かみやま あきお



