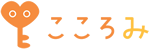AIに勝てる聞き上手
2025.05.17

はじめに
最近、AIの進化が加速していると感じる方も多いのではないでしょうか。いよいよホワイトカラーの仕事への影響が目に見えてきたように思います。今後、情報処理能力においてAIが人間をはるかに上回っていく中で、ビジネスの現場で人間が勝てる領域はどこになるのでしょうか。コミュニケーション、特に「聞くこと」はその有力な候補となりそうなものの、幅広い「聞く力」全体だけでは、具体的な行動に結びつけるのは難しそうです。では何を意識すべきでしょうか。本記事では、こうした問いについて考察します。
AIの急速な進化

近年のAIの進化は目覚ましい。これに異論をはさむ余地はないでしょう。そして社会への浸透も本格化してきました。こころみがAIエージェント構築サービスを企業に提供している中でも、社員がChatGPTなどを活用するのは当たり前になってきており、むしろAIをいかに社内・対外業務で効率的に、実践的に使えるかという相談が増えてきているように思います。
業務におけるコミュニケーションに関していえば、メールのやり取りや事務的な説明、物事を列挙したり整えて説明文章を作るなどは任せられるレベルに達していると言えます。一方で、情緒的なコミュニケーションについてはまだまだ人間のほうが能力が高いという声も聞かれます。例えば営業職などは残り続けるのではないか、といった説もあります。
セールスフォース社の営業担当のみ採用する、の意味

実際に、世界のITサービスのトップ企業であるセールスフォース社の創業者マーク・ベニオフCEOは、2025年度はエンジニアを採用しないと宣言し、一方で営業担当者の採用を進めています。
SalesforceのCEOが「AI導入が成功したので今年はエンジニアを雇わない」と発言
ほかならぬ顧客管理の専門企業であるセールスフォースの戦略は非常に興味深いものがあります。もちろんこれがずっと続く保証はないわけですし、初期アポ獲得フェーズなどは代替が進んでいると思いますが、少なくとも現時点においては、エンジニアはAIで代替できるが営業はそうではないと判断している。AIでは代替できない、人間ならではの高度な対人スキルや共感力、信頼関係構築能力などを特に重視していると考えられます。複雑な顧客のニーズを深く理解し、情緒的なつながりを築きながら、個別最適な提案を行うといった能力が、AI時代においてもなお競争優位性の源泉となり得ると判断しているのかもしれません。
共感的理解の価値

ここで言うAIに代替できないコミュニケーション能力とは、いわば「共感的理解」の能力であると言えるでしょう。共感的理解とは、話し手の心情およびその背景を把握し、聞き手の経験および心情から近い感情を描くことです。これは、客観的な事実や因果関係を把握し、構造化・抽象化を目指す「論理的理解」 とは異なります。共感的理解の目的は、何か課題を解決することではなく、情緒を安定させることと、お互いの信頼関係を醸成することにあります。共感的理解においては、真実は話し手の中に複数存在すると考え、話し手の言うことを受け止め、考えや意志を大切にする、すなわち相手を尊重する 姿勢が重要になります。
このような共感的理解に基づいた信頼関係が構築されると、話し手はネガティブなことや話しにくいことも含めて、より率直に話せるようになります。これらの能力は人間特有でもあり、人間だからこそできるのだ、という立場は一定の説得力を持つように思います。
囲碁・将棋との比較

一方で、私はこういうケースを考える場合に、常に囲碁・将棋の事例を思い出すようにしています。アルファ碁が世界最強の囲碁棋士だったイ・セドルを破ったのが2016年、Ponanzaが佐藤天彦叡王を破ったのが2017年です。囲碁においては2016年、将棋においては2017年にAIが人間の実力を上回った、と言えるでしょう。
同じ意味合いで、AIがコミュニケーション能力において人間を超える日がくるか、と言われるとこれは難しそうな印象があります。世界最高の共感的能力を持っている人よりもAIのほうがコミュニケーション力で上回るイメージが湧きません(もっとも、共感的能力の世界王者を決める大会がどのようなものになるのか想像もつきませんが・・・お互いが悩みを相談しあうことになるのでしょうか)。
さて、囲碁・将棋に再び立ち返って考えてみましょう。世界チャンピオンが負けたのは比較的最近といえますが、大多数の人間はそのずっと前から、囲碁でも将棋でもコンピュータに勝てなかったのではないでしょうか。そもそも囲碁も将棋もできない人もたくさんいます。今でも覚えていますが、小学生のころ私はクラスの中で将棋が一番強かったのですが、「ファミコン将棋」の最後の敵に一度も勝てませんでした。40年以上前から、人類の大半は将棋においてコンピュータの実力を下回っていた、と言えます。
コミュニケーションにおいてはどうでしょうか。実のところ、AIでもAIでなくても、プログラムは毎朝必ずあいさつをできます。・・・朝あいさつをできない人、身の回りにいませんか。あいさつはできたとしても、今のAIのコミュニケーション能力を考えると、人類の半分くらいはすでに敵わない状況になっていると言えないでしょうか。これは共感的理解力の側面においても、すでにそうなっていると言えそうです。現時点で「平均的な聴き手」はAIに負けていると言ってもいいかもしれません。
今はまだトップランクに入る営業マンやカウンセラーであれば勝てるかもしれない。しかしそれもこのAIの進化速度であれば、早晩に追いつかれる可能性はある。少なくとも24時間対応可能であることやコストメリット、記憶容量など勝てない要素もすでに多くあります。
人間の勝ち目

では、人間に勝ち目はないのか。私は「完璧でないからこそ理解をしようと頑張ってくれること、そして話し手の影響を受けて変化すること」という点、つまり「真剣に話を聞いて感銘を受けること・感動すること」が人間の勝ち目ではないかと思います。
これは人間ならではの特性と深く結びついています。まず人間は、不完全な存在でそれを自覚しています。相手を理解しきっていないからこそ理解しようと努めます。AIはどうでしょうか。自分が相手を理解しているかどうかなど関係ない。相手の発言を受け、AI自身の持つアルゴリズムで処理をするだけです。理解している/理解していないという概念が初めから存在しません。
次に人間は、目の前の話し手との相互作用を通じて、その場の雰囲気や話し手の微細な表情、声のトーンなど、個別的で流動的な情報をもとに感情を共有し、自身の経験と照らし合わせながら共感し、変化していきます。そして、話し手の心の変化や、話された言葉の裏にある背景に寄り添いながら理解を深めます。これは、事前にプログラムされたアルゴリズムで処理するAIには真似のできない、極めて人間的で、その場限りの個別的なプロセスです。
以前「お釈迦さまは聞き上手なのか?」という考察をしました。AIは人間よりもお釈迦様に近いと言えるかもしれません。もちろんプロンプトエンジニアリングとRAGを使い、対話履歴に基づいて会話内容を変えていくことはできます。しかしそれは相手を理解しようとしている姿勢だとも、話し手の影響を受けてAI自分自身が変質したことでもない。AIと話しても、AIが私の話を聞きたいと願うわけでも、AIが私の影響を受けてAI自体が変化するわけでもない。
人間は、自分に興味を持ってほしい欲求と、会話を経て相手に影響を与えたい欲求がある。それはわたしたちこころみが長年、自分史作成のサービスを提供する中で強く感じていることでもあります。私の人生に興味を持ってほしい。そのうえで自分が生きてきた証拠を、他者の認識の中に影響として残したい。単なる記憶ではなく、他人に影響を与えることで自分が生きた証としたい。そうした根源的な欲求を人間は持っているのではないか。
改めて。人の話を聞いて自分自身が変化することは、人間にしかできません。そう考えるとまだまだ希望があると思いませんか。「あなたの言葉に私は動かされた」 という感情を伴う変化こそが、人間固有の価値であり続ける——私はその可能性に賭けたいと思います。皆さんはいかがでしょうか?この文章で、皆さんの考えが少しでも変わることを、私は願っています。
株式会社こころみ 代表取締役 神山晃男