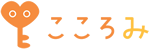環世界と聞き上手
2022.09.11

「環世界」という概念があります。生物から見た世界のあり方の表現ですが、人間個人個人から見た世界の見え方としても使える概念です。今日は環世界と聞き上手がどんな関係にあるのか、考えてみました。
環世界とは何か?
1933年、ドイツの生物学者であるユクスウェルの提唱した概念です。すべての動物はそれぞれに主特有の知的世界を持っていて、それを主体として行動・生活しているという考え方です。空間だけでなく、時間の進み方も生物にとって異なると説きます。
当初、進展著しい科学のものの見方では、唯一絶対の真理があると思われ、そうした考えを否定するかのような立場であった環世界という概念は、広く受け入れられなかったようです。晩年に友人の助けを借りて大学内に研究所を作ることができたようですが、大きな学派にはなりえませんでした。
しかしながら、近年になってこの考え方がいろいろな学問の中で再注目を集めているように思えます。科学が進歩したことによって、主体の数だけ世界があるという考え方にようやく理解が追い付いてきたのかもしれません。
ダニの世界

さて、そんな環世界の例として、ダニの例が最もわかりやすいと思われます。マダニというダニは、森に棲んでいて、動物が通るのをじっと待っています。哺乳動物が近づいたのを酪酸のにおいで感知して、枝から飛び降ります。毛についたマダニは、温度感覚によって温度が高い方向、つまり皮膚の表面に潜り込み、嘴を皮膚にさして生き血を吸います。この時、マダニには、森のそよ風も、草木の発するさわやかな香りも、遠くに見える山脈の輝きも存在しません。マダニの世界に存在するのは酪酸、温度、液体のみです。酪酸を発するのが動物かどうかも関係ありません。実験用に作られた模型に入っている食塩でも関係なく飲み、そして地面におちて産卵します。マダニが生きる世界は、我々人類が思うものと大きく異なるのです。
そんな風に、生物の数だけ世界のあり様は異なるとユクスウェルは説きます。マダニにはマダニの、犬には犬の、コウモリにはコウモリの、そして人には人の環世界があるわけです。私たちは、森というと緑色の木々に包まれ、遠くから鳥の声が聞こえ、歩けば土を踏みしめる感覚があるあの場が真実として存在すると思っていますが、それも人間にとっての環世界であるにすぎないわけです。真実の森そのものとは大きく異なる。というよりも、真実の森というものが存在するわけではないわけです。
時間も同様です。人間は、1/18秒より短い間隔で動くものを認識できません。だから映画は、1/32秒ごとに画面を切り替えて映写し、人はそれを自然に動いている/止まっているものとして認識しているわけです。この認識の感覚も生物によって異なり、ベタという魚では1/50秒(人間より早い)、カタツムリは1/4秒だそうです。世界の動き方も全然違うわけで、ベタの感覚では、世界は我々の3倍近くゆっくり動いていると言えるかもしれません。もっとも、それすらも異なる環世界なので、ゆっくり動くという概念自体が異なる可能性が高いですが。
魔術的環世界

さらにユクスウェルは踏み込んで、真実というもののあいまいさに鋭く切り込みます。「魔術的環世界」が存在すると説くのです。主体にしか見えない現象が現れる環世界が立ち現れると。例えば、ある少女はマッチ箱とマッチで遊びながら、「魔女が現れた!だれか魔女をやっつけて!」と叫ぶ。その時彼女には、ありありと魔女の姿が浮かんでいるはずです。彼女の環世界には、魔女が確かに存在するということです。
お化けであれば、「そんなものの存在を信じるのは程度が低いからだ」といって片付けてしまえるかもしれません。しかし、実は私たちは自分たちで想像したものが実在すると固く信じることで、この社会を成り立たせています。「国家」というものは存在するでしょうか。「お金」というものは?お札という物理的なものは確かに存在するとしても、そこに宿る価値を私たちはどうやって世の中に確かにあると認識しているのでしょうか。神もそうです。むしろ「サピエンス全史」でハラリが述べていたことは、ホモ・サピエンスは「魔術的環世界」を作る能力に長けていたからこそ発展したのだ、ということだと解釈できます。
宇宙物理学者的環世界

さらにさらに、ユクスウェルは、宇宙物理学者に見える環世界についても言及します。宇宙物理学者が宇宙を見たときに見える景色は、一般人が見たものと大きく異なる。惑星同士の動き、何十億年を超えた恒星や銀河の動き、爆発、そして静寂。そうしたイメージ自体が、宇宙物理学を学んでいない人から見える世界と大きく異なるということです。
そしてそれは、宇宙物理学だけでなく、あらゆる人間にも当てはまることに気づかされます。すべての人はそれぞれが持っている感覚器も、経験も、知識も違います。当然のことながらそれぞれの環世界は異なり、異なる環世界から見た同一のもの、例えばリンゴですら意味合いの異なるものとしてとらえられることになります。ある人にとってリンゴとは食欲を満たすためだけのものでしょうし、ある人にとっては故郷を思い出させる重要な過去の小道具かもしれません。そうして、環世界の数だけ、ある対象をとってもある人をとっても、社会という広い対象をとっても、それぞれに正しい像が存在するということが理解できます。
環世界的世界観

1933年の段階でこれだけのことを主張していたのに改めて驚かされますが、このような考え方が、デジタル化、ネットワーキングによって人間そのものの存在や意識、感覚が拡張されている現在において改めて見直されているというのも、納得できるように思います。
改めて強調するとすると、世の中には事実はなく、主体の数だけ真実/世界が存在する、ということだと思います。
いわば、環世界的世界観、といっていいかもしれません。
それでは人間同士でもあっても真の理解は難しいのか。あるいはそうかもしれません。ただ、たとえば国分巧一郎という哲学者は、その著書の中で、環世界を移動できる能力こそが人類の特徴であると述べています。本当に異なる環世界に移ることは難しいかもしれませんが、想像し、そこに近いところに移ることはできると言えるでしょう。例えば物理学者が想像する宇宙の世界も、学ぶことで確実に近くには行けると言えるでしょう。
こうした考え方は、弊社が追い求める「聞き上手」の世界観に非常に親和性が高いと考えます。
環世界をまたがるコミュニケーション手法が聞き上手である

一言で言ってしまえば、話し手の環世界を想像し、移動しようとすることが聞き上手である、と言えるのではないでしょうか。すなわち想像力を働かせて、その時の感情も含めた話し手の環世界に身を委ねる行為。それが聞き上手であると言えます。そうすると、聞き上手に必要とされる能力として、共感力であったり、暗黙的理解であったり、が挙げられているのがすとんと腹落ちするのではないでしょうか。
もちろんここで、環世界をまたがることが可能であるといいきってしまうことは勘違いにほかなりません。他人の環世界に完全に移ることはできない前提で、それでも少しでも近い環世界を再現しようとする行為、それが聞き上手なのだと考えます。
聞き上手が目指す世界はとは、自己承認、感覚の重視、真実の相対化でした。まさにこれこそ、他者の環世界を前提として、自分の環世界も受け入れたうえで他者の環世界に興味を持つ姿勢であると言いかえられるのではないでしょうか。
こころみは、これからも環世界の移動のために聞き上手を使い、少しでも多くの方と環世界を共有していきたいと考えています。
株式会社こころみ 代表取締役社長 神山 晃男